水戸市民会館
芸術・文化の発信拠点 市民のサードプレイスが完成
芸術と文化が刻まれてきた歴史ある街・水戸市の再開発事業の一環として、東日本大震災で被災した市民会館の移転が決定。2023年7月、中心市街地に水戸市民会館がオープンしました。多くの事業者が関わる中、世界的な建築家の構想力を引き出しながら、複雑な制約下で発注者の想いをいかに実現したのか、プロジェクトメンバー7名が当時を振り返ります。

水戸市民会館
グロービスホール(大ホール)、ユードムホール(中ホール)、会議室及び展示室等で構成された市民会館。再開発事業の一環として整備、2023年7月に開館。市民の芸術文化活動や賑わいや交流を創出する拠点として、水戸市の中心市街地に位置している。

話し手のご紹介
再開発事業の複雑な課題を解決した“連携”
 水戸市が実施したプロポーザルにおいて個別に選定された伊東豊雄建築設計事務所と横須賀満夫建築設計事務所が結成した共同企業体によって設計が行われ、施設全体に耐火木部材が大規模に採用された。4層の吹き抜け空間「やぐら広場」は、縦横の梁が互いに支え合うようにやぐら状に組まれた木トラス構造になっており、訪れる人々を圧倒する。
水戸市が実施したプロポーザルにおいて個別に選定された伊東豊雄建築設計事務所と横須賀満夫建築設計事務所が結成した共同企業体によって設計が行われ、施設全体に耐火木部材が大規模に採用された。4層の吹き抜け空間「やぐら広場」は、縦横の梁が互いに支え合うようにやぐら状に組まれた木トラス構造になっており、訪れる人々を圧倒する。一目で気に入りましたが、コストの問題をどうやって解決していくか考えました
水戸市民会館の建設の経緯を教えてください。
- 海老澤
- 水戸市民会館は、東日本大震災により使用できなくなったため、移転が検討されました。
- 鯉渕
- 現在の水戸市民会館がある場所は、再開発事業を進めていた地区です。昔は水戸駅前から泉町までアーケードが続いていて、休日は肩と肩が触れ合うくらい人通りが多かったのです。しかし徐々に大型店舗の郊外化が進み、いつしかシャッター商店街になってしまいました。そこで、昔の賑わいを取り戻そうと再開発計画が進み、1990年に水戸芸術館、2006年に京成百貨店が整備されました。その他にもさまざまな計画もあったのですが、公共施設の改修に焦点を絞り始めた頃、東日本大震災がありました。
- 海老澤
- 震災で水戸市役所や旧市民会館、その周辺道路を含め全部被災しました。市民会館としての機能を失ったので、早急な再建が望まれ、本市の中心市街地である泉町に移転することが検討されました。ここにはすでに水戸芸術館もあったので、「芸術文化の2大交流の拠点に」というキーワードも生まれました。
- 磯前
- 私たちにとって、市街中心部の活性化は常に課題としてあります。その課題を実現させるためにも、集客施設である市民会館を活かさない手はありません。そこで震災から2年後の2013年には移転することが決まりました。
設計者はどのように選定されたのでしょうか。
- 谷口
- 再開発事業は地権者の合意により事業を進めるので、権利者が主体となるのが基本です。しかし、市民会館という専門性の高い建物をつくるということもあって、再開発組合(以下・組合)ではなく、市に設計者選定のプロポーザルの実施をお願いすることになりました。
- 海老澤
- もちろん組合さんと協議して、ご了承をいただきながらの実施です。全国規模で実績のある設計事務所と地元に精通した設計事務所を別々に審査し、それをお見合いさせるという、やや特殊なプロポーザルでした。結果、伊東豊雄建築設計事務所と横須賀満夫建築設計事務所が共同企業体を結成して、設計を担うことになりました。
- 小倉
- 専門性の高い高度な提案に対し、組合さんは期待や不安がありましたか?
- 鯉渕
- 資料を見て、これはもう決まりだなと思いましたね(笑)。ただ、唯一心配だったのは費用です。
一般的な市の公共工事と異なる点や難しさはありましたか?
- 海老澤
- そもそもそれぞれのゴールが違うんです。たとえば組合さんは地権者の意向を汲む。ただその要望を100%取り入れると、搬入ヤードが狭くなる等、使い勝手が悪くなってしまいます。逆に、市としても地権者の意向をないがしろにはできません。そうした問題を補うために、我々は違うセクション、しかも担当副市長が異なる部局間で連携会議を行いましたし、設計者さんが決まった後には組合さんと我々、さらに設計者さんを含めた会議を週に2~3回は開き、情報の共有を徹底しました。再開発を進めることと、文化ホールをつくるということをすみ分けしつつ、お互い良いところを補完するような進め方です。
- 谷口
- 事業者である組合、再開発を指導・監督する市の部局、最終的に市民会館として引き取る市の部局との間には気持ちのぶつかり合いがあったと思いますが、“良い街をつくる”という目標が終始一貫していました。結果的にいい関係が築けたのではないでしょうか。
- 伊藤
- 今回はプロが集まっていたのが大きな利点だったと思います。設計者にせよ、施工者にせよ、同じ目標に向かって着手できたという実感はありますね。それと、タイミングが良かったとも思います。消費税が経過措置を使って10%になる前に契約を結んだり、木材も価格高騰の前に契約を済ますことができました。一部、鉄骨はちょっと価格が上がったにせよ、物価高の影響をそれほど受けずに、市の力も借りて終結できたのだと思います。
- 小倉
- 最近、大規模な木造建築の計画が各所で発表され、どこも話題になっています。今回もタイミングとしてはアピール度の高いものになりましたよね。
 水戸芸術館(手前)と水戸市民会館(中央)、京成百貨店(奥)の3施設愛称を「MitoriO(ミトリオ)」と決定。水戸市の中心的な賑わいの拠点が生まれた。
水戸芸術館(手前)と水戸市民会館(中央)、京成百貨店(奥)の3施設愛称を「MitoriO(ミトリオ)」と決定。水戸市の中心的な賑わいの拠点が生まれた。 茨城県内最大の2,000席を有するグロービスホール(大ホール)。観客席は3層構成で、催しの規模に応じてスペースを変更できる。GRCでつくられた梅がモチーフの音響反射板は5型・5色。壁面はRC小たたき仕上げ、背面壁は吸音カーテン、客席は背板がつながったデザインになっている。
茨城県内最大の2,000席を有するグロービスホール(大ホール)。観客席は3層構成で、催しの規模に応じてスペースを変更できる。GRCでつくられた梅がモチーフの音響反射板は5型・5色。壁面はRC小たたき仕上げ、背面壁は吸音カーテン、客席は背板がつながったデザインになっている。
プロジェクトに関わったマネジャー
関連する用途
-
公共
2014年6月に「公共工事の品質確保の促進に関する法律」が改正され、公共工事においても多様な発注方式の採用が認められたことで、DB(デザインビルド・設計施工一括発注)方式、ECI(施工者が早期に関与)方式などが普及しつつあります。一方で、自治体の技術職員が減少する中で、2020年9月には「地方公共団体におけるピュア型CM方式ガイドライン」が発行され、複雑化・高度化する事業をCM活用により着実に推進する手法が広がりをみせています。また、多くの自治体では高度成長期に建設された施設の老朽化が進み、PRE戦略や公共施設マネジメントの立案・実施も課題となっています。
-
まちづくり/複合施設
近年「まちづくり」や「複合開発」は一段と複雑化しています。事業主のビジョン・想い、立地、地域課題、マーケットの状況、都市計画の位置付けから納期、予算にいたるまで、諸条件によって大きくプロジェクトのあり方が異なります。通常の建設プロジェクトよりも長期にわたり、10年以上の時間を要することも少なくありません。関係者の数も膨大です。そこで重要となるのが、ブレないコンセプトと変化に柔軟に対応できるスキームの構築。創造力と実現力のある最適なプレイヤーが適切なタイミングで事業に参画することもプロジェクトの成否を左右します。
-
教育/文化/アート
少子化が加速する社会において、学校づくりも新たな局面を迎えています。老朽化の進む学校施設を、品質などの標準化を図りながら整備したり、場合によっては民間からの活力を導入する仕組みや、施設の統廃合を視野に入れた検討も行わなければなりません。私立学校では学生獲得戦略に基づいた、ブランディングや魅力ある施設づくりも重要です。また文化・アート施設では、多様化する社会のニーズに応えるため観賞を主眼に置いた施設から体験型、食事や買い物も楽しめる複合型やリアルとバーチャルの融合への対応など、施設の役割・機能の転換が進みつつあります。
関連するプロジェクトストーリー
-
Story46
SAGAサンライズパーク
街の賑わい、経済の循環を生み出す 佐賀の新しいランドマークが誕生
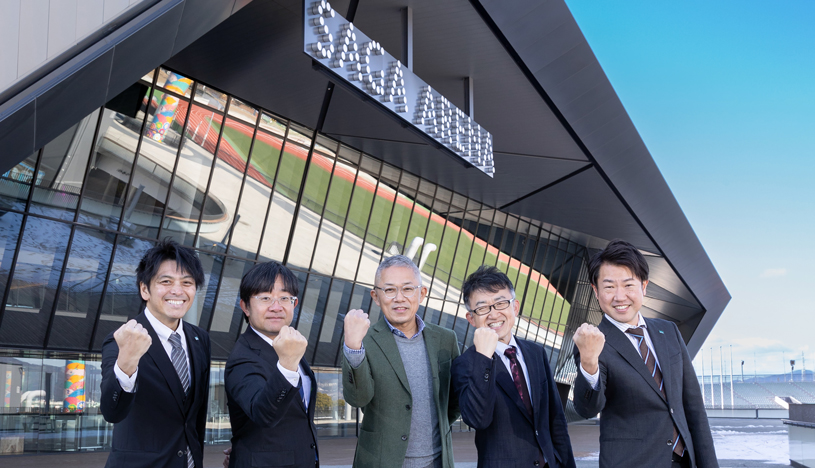
-
Story38
長崎市交流拠点施設PFI事業
3事業4施設建築プロジェクトでの横断的マネジメントで代表企業をサポート
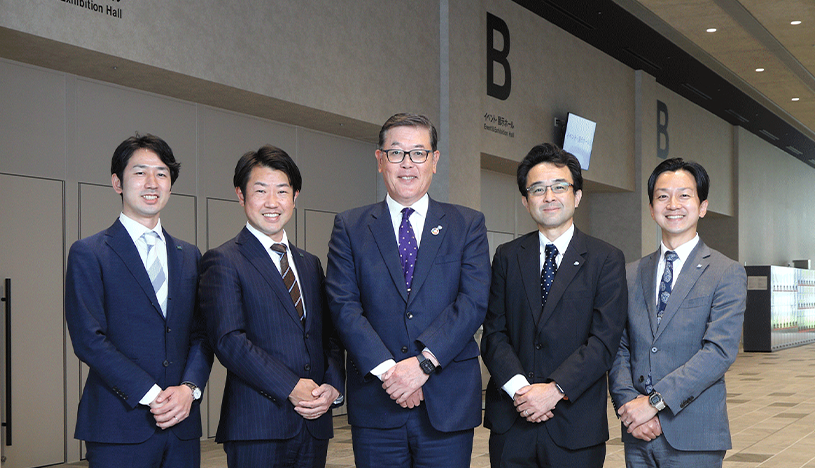
-
Story30
横浜市役所新庁舎 基本設計からDB方式を初めて採用した公共施設が完成
基本設計からDB方式を初めて採用した公共施設が完成

-
Story27
山梨県 丹波山村 役場 新庁舎 土地の空気を感じながら、これまでにない新しい「村」をつくる
土地の空気を感じながら、これまでにない新しい「村」をつくる
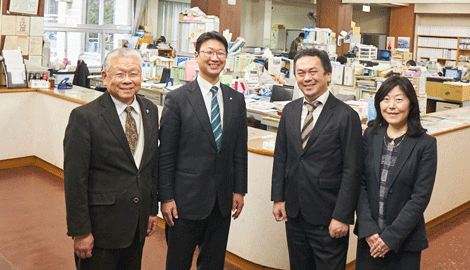
-
Story20
大熊町役場新庁舎:令和初の新庁舎完成 公共施設建築でデザインビルド方式を活かすノウハウとは?
令和初の新庁舎完成
公共施設建築でデザインビルド方式を活かすノウハウとは?
-
Story16
女川町地方卸売市場
地域経済の要を復興させた最高のチーム

-
Story09
石巻市水産物地方卸売市場
アットリスクCM方式で迅速に魚市場を再建







