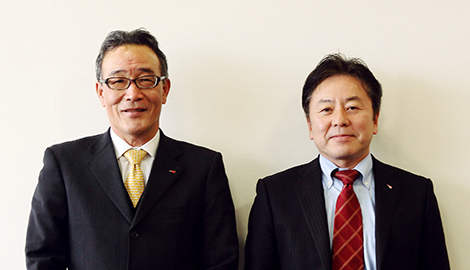キオクシア 横浜テクノロジーキャンパス Flagship棟
偶発的な出会いと発想を生む 人と技術のイノベーションの発進へ
進化と変化の目覚ましい半導体業界で2019年、新しい社名で出発したキオクシア株式会社。デジタル社会の未来を担うNAND型フラッシュメモリとSSDメーカーが求めたのは、分散していた技術研究部門を集約できる拠点と、技術者たちが活発にコミュニケーションを取れる環境でした。

キオクシア株式会社 横浜テクノロジーキャンパス Flagship棟
世界初のNAND型フラッシュメモリを開発した東芝から2017年、メモリ事業を会社分割で継承。2019年にキオクシアに社名を変更した。これまで分散していた技術研究部門を集約するため、同社の研究開発拠点である神奈川県横浜市の横浜テクノロジーキャンパスにFlagship 棟を建設することが決定し、2023年10月に竣工。

話し手のご紹介
-
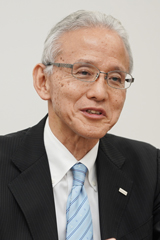
小林英行さん
キオクシア株式会社
横浜テクノロジーキャンパス 所長 -

岸上大三さん
キオクシア株式会社
横浜テクノロジーキャンパス
企画管理担当 参事
-

岩下孝樹
株式会社山下PMC
プロジェクト統括本部事業推進部門 3部
チーフプロジェクトマネジャー -

池田裕一郎
株式会社山下PMC
環境・運営推進本部 3部 IT戦略部
プロジェクトマネジャー
分散している人材と技術を集約した最先端の拠点を
 Photo:株式会社エスエス、島尾 望
Photo:株式会社エスエス、島尾 望第三者の客観的な視点が必要だと思い、設計・施工会社の決定後にご参画いただきました
横浜テクノロジーキャンパスに、新棟としてFlagship棟を建設された目的について教えていただけますか。
- 小林
- 当社が株式会社東芝から独立したのが2018年です。当時は拠点が東芝の各事業所に分散していました。分散しているメンバーと技術を集約する新しい拠点が必要でした。これが第一の目的です。
メモリ事業部とSSD事業部が当社の両輪です。両事業の技術者のコミュニケーションを密に図ることで我々の技術を明確に推進さ せる、そのためには拠点の集約は必須だと考えました。 - 岸上
- 目覚ましいスピードで進化、拡大する半導体市場において、研究開発から製品評価、顧客対応など、相当なスペースを必要とします。分散に伴う非効率な面があるので、一カ所に集約し運営を効率化する必要がありました。
プロジェクトの経緯を教えてください。
- 小林
- 2019年に清水建設さんに相談して基本計画を作り、発注図書を整備しました。施工も結果的に清水建設さんに依頼することになりました。設計と施工が同じ会社になるため、第三者の視点を入れた適切なプロジェクト運営と判断のプロセスを求め、CM会社を導入しました。
- 岩下
- 当社は設計・施工会社を決定する前からご支援させていただくことが多いのですが、今回は少々イレギュラーなパターンです。
- 岸上
- 今回はA工事だけでなく、C工事や移転計画もお願いすることになりました。主要会社だけでも10社以上に及び、そのすべてを束ねて動かすハンドリングをご支援いただきました。スケジュール面では、いろいろ無理を聞いていただきました。
- 岩下
- 私たちにとっても、これまで経験したことのないチャレンジングなプロジェクトになりました。
ネックはセキュリティとコミュニケーションの両立
Flagship棟はどのようなコンセプトで設計されたのですか?
- 小林
- ここには技術者同士が密にコミュニケーションを図ることができ、イノベーションが生まれる環境が求められました。皆が開放 的な気持ちになれる、意見交換しやすい、明るい空間を目指しました。
たとえば執務室は、フロア全体の端から端まで見渡せる、柱のない広大なメガフロア空間になっています。 - 岸上
- 機密性の高い最先端技術を取り扱っているため、厳格なセキュリティが求められますが、最大のネックは厳しいセキュリティと コミュニケーションの両立でした。部屋毎にセキュリティを設けると、技術者同士のコミュニケーションを損なうおそれがあります。
コミュニケーションを活性化する上で留意したのはコア業務に集中できる空間と技術者同士の交流を促進する環境の構築でした。そのために各技術者の意見を取り入れながら、設計に反映させていきました。
象徴的な場所が、吹き抜けエリアです。トップライトからの日差しによって明るく、リラックスでき、自然に人が集まってくるような空間にしました。
もうひとつが吹き抜け階段です。交差型にしてどの階のどのエリアにも行きやすく、かつ、他の移動中の人が見えるので声を掛けやすくなっています。このように偶発的なコミュニケーションが生まれるような仕掛けを取り入れました。
コロナ禍の制約下で基本計画も予算も再確認
あらためて。山下PMCにCMを依頼したことを、どのように評価をしていますか?
- 小林
- 建物の設計及び工事を第三者の目で管理していただいたことに加え、基本計画についても客観的にチェックしていただけたこと が、プロジェクトの遂行につながりました。
- 岸上
- 2019年の11月から山下PMCに参画して頂いたのですが、この時期は東京2020オリンピック・パラリンピックの影響もありました。鉄骨やケーブル、その他の建築資材が高騰して、建築コストが膨らんでいきました。岩下さんたちから豊富な経験を踏まえた的確な判断材料を提示してもらい大変助かりました。
- 岩下
- しかも、プロジェクト期間のほとんどがコロナ禍と重なってしまいました。
- 岸上
- 世の中が異常な状況でしたから、資材の納期が長くなる、作業者の確保が困難になるなど、何事も予定通りには進みませんでし た。その分、迅速に、臨機応変に判断しなければならないことが多くありました。そんな状況で山下PMCから適切な情報と的確なア ドバイスが得られたことが良かったと思います。
- 岩下
- 今回のプロジェクト、私たちはゼネコンさん決定後の参画と申し上げましたが、基本計画も確認させていただきました。すると、まだ曖昧な部分がかなり残っていました。そこで、スケジュールには多少影響するけれども、はじめの数カ月、条件整備という期間を設けて、それから設計に移るというご提案をいたしました。それを小林所長と岸上さんが受け入れてくださったおかげで、計画の抜けや漏れの確認、課題の洗い出しができました。
- 小林
- 結果的にコストも当初予算より10%増ということが判明して、それがコスト削減への基点になりました。
- 岩下
- 共通認識を持って進められたのがよかったと思います。
 コミュニケーションの場としてデザインされた中央吹き抜けエリアの交差型階段。幅を広く取り、移動しやすさを確保。あえて階段を利用することで、他部署の人との偶発的なコミュニケーションが期待できる。階上階下からも、階段を行き来する人が見える。Photo:株式会社エスエス、島尾 望
コミュニケーションの場としてデザインされた中央吹き抜けエリアの交差型階段。幅を広く取り、移動しやすさを確保。あえて階段を利用することで、他部署の人との偶発的なコミュニケーションが期待できる。階上階下からも、階段を行き来する人が見える。Photo:株式会社エスエス、島尾 望
プロジェクトに関わったマネジャー
関連する用途
-
R&D/生産施設
市場の構図やニーズがめまぐるしい変貌を続けるなか、経営戦略のイノベーションとともに研究開発のあり方を見直す企業が増えています。従来の研究開発施設は、研究開発部門主体で計画・整備・運営されてきましたが、近年の研究開発は、企画段階から運営段階まで、経営戦略を色濃く反映する方向へと転換し始めています。その際にカギを握るのは、経営と直結する「事業(研究開発)戦略」の立案です。経営戦略というトップダウンの判断と、研究開発運営というボトムアップの提案を統合した事業戦略を立ち上げ、それに基づく研究開発施設の構築が求められています。
関連するプロジェクトストーリー
-
Story39
H.U. Bioness Complex
つなぐ・みせる・はぐくむ ~ ヘルスケアにおける新しい価値の創造 ~

-
Story34
ファンケル美健 千葉工場 マイルドクレンジングオイル 専用生産棟
施設づくりを通じた事業づくりのお手伝い
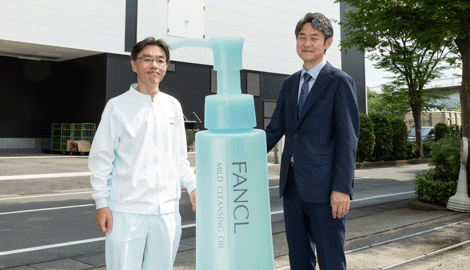
-
Story29
ボーケン品質評価機構 大阪本部ビル 試験担当者のアイデアが凝縮された施設
試験担当者のアイデアが凝縮された施設
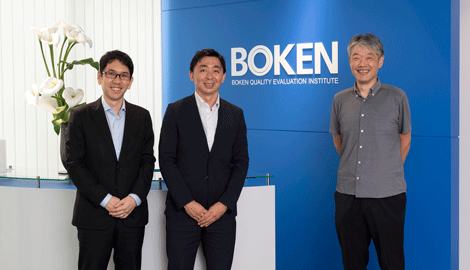
-
Story26
加賀マイクロソリューション 福島事業所 発注者、設計者、施工者、CMがワンチームで完成に導いた“人が集まる”新工場
発注者、設計者、施工者、CMが
ワンチームで完成に導いた“人が集まる”新工場
-
Story08
白河オリンパス 白河事業場本館棟
医療機器トップメーカー生産拠点の、大規模再開発
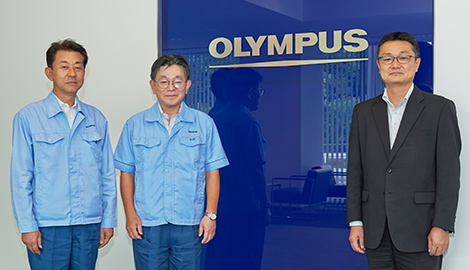
-
Story04
東京水産振興会 豊海センタービル
オーナー、テナント両者の納得を引き出す
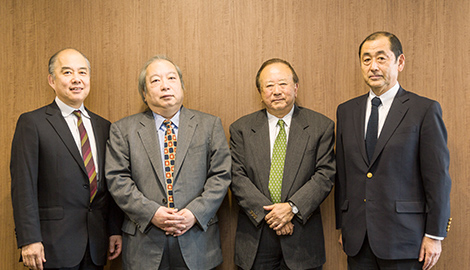
-
Story02
矢崎総業 / 矢崎部品 ものづくりセンター
「ものづくり」から「営みづくり」へ