The Report #20 ストック型社会における施設運営の最適解とは
4か月ぶりのThe Reportは、山下PMCで施設保全マネジメントを専門とする環境・運営推進本部 1部CRE戦略部 チーフプロジェクトマネジャー 渡辺和夫がご紹介します。
施設のストック活用については、「The Report #15」でも取り上げました。今回は、オフィスビルの価値の維持・向上につなげるためのポイントを中心に解説します。

フロー型からストック型への変化~時代と共に変化するオフィスビルの価値観~
かつての高度経済成長期において、日本のオフィスビル市場はスクラップ&ビルドに代表される「フロー型」が主流でしたが、バブル崩壊を契機に「フロー型」の開発は急速に減速。新築による価値創造よりも、既存施設の価値をいかに維持・向上させるかという「ストック型」の運用が重視されるようになりました。
ストック型運用を成功させるためには、施設のライフサイクル全体を見据えた保全計画の策定と実行が不可欠です。本コラムでは、山下PMCが提供する施設運営段階におけるサービスの中核である「保全計画の策定手法とその実行プロセス」について、具体的な事例を交えながらご紹介します。

施設運営段階におけるサービス「Facility doctor®」のうち、渡辺が担当する案件の1つ『新宿アイランドタワー』の全景。予算化、更新・改修仕様策定、工事管理支援など、その業務は多岐に渡る
保全計画策定手法~潜むリスクと回避策~
一般的な保全計画は、BELCA(公益社団法人ロングライフビル推進協会)などが提唱する指標や、定期的に行う劣化診断の結果を基に30年前後の長期修繕計画を策定することから始まります。これにより、建物の健全性を維持しつつ資産価値の低下を防ぐことが可能になりますが、しかし、こうした計画は往々にして改修等工事費の肥大化だけでなく、特定年度に工事費支出が集中し、修繕積立金会計を圧迫するリスクが潜んでいます。
これを回避するためには前述の一般的な計画に加え、以下に代表される施策により支出のミニマム化や平準化を図ることが重要です。
2) リスク分析を踏まえた上での予防保全から事後保全への見直し
3) 予防保全から予兆保全、予知保全への見直し
では、見直し方法の具体的内容について触れていきます。
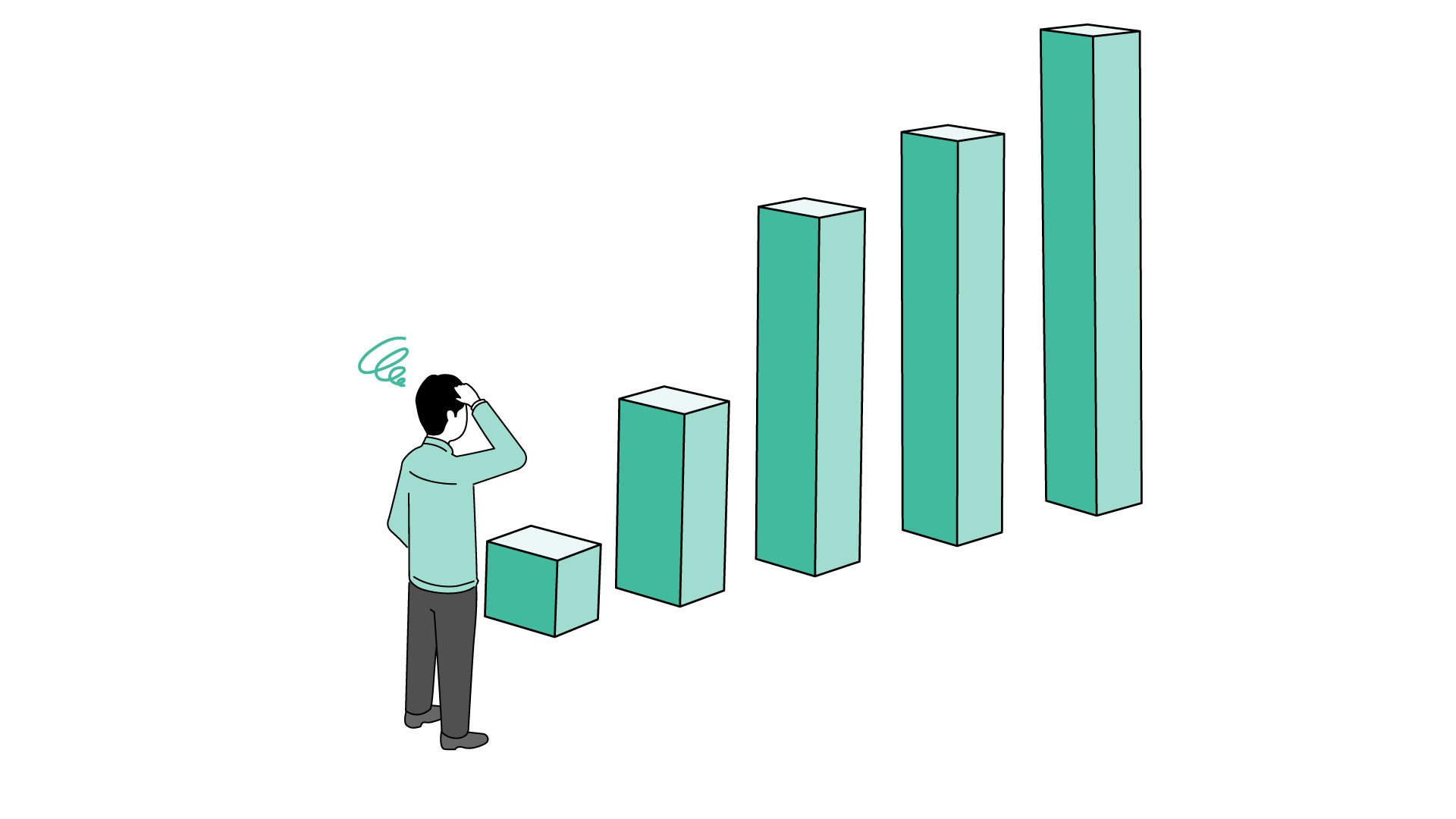
1) 優先順位を見極めた上での工事実施時期見直し
建物を構成する部材や機械、部品などにはそれぞれ役割があり、一つとして無駄なものはないはずです。それゆえ“順位付け”は大変な悩みどころですが、限られた資金で施設運営を継続するためには、何らかの判断基準を以て順位付けをし、前倒しや後ろ倒しといった入れ替えを行う必要があります。
その基準は立地、規模、構造などによって変わるため一概に正解と呼べるものはありませんが、①安全性、②テナント満足度、③施設運営に与える影響などは、前述条件に問わず比較的多くの案件で重視されてきた判断基準です。
たとえば①安全性でいえば、更新や改修をしないことで、施設関係者の生命や健康に影響を与えてしまうものは無いか?といった切り口で該当するアイテムを抽出するところから検討を開始し、さらに影響の大きさから順位付けをする、といった手法は多くの施設で取り入れられてきました。
2) リスク分析を踏まえた上での予防保全から事後保全への見直し
不具合や故障(以後、故障等)のリスク回避といった観点でいえば予防保全(状態基準や時間基準の観点から、不具合が発生する前に更新または改修する保全方法を示す)は最も有効な方法でしょう。ただしこの方法は、ひょっとしたらまだまだ寿命を迎えない設備までをも更新または改修してしまう可能性があり、工事費増大を招きやすい側面があります。
そこで故障等が発生した時のリスク、故障等から復旧に要する期間やこの間に起こる損失、これらネガティブ要素を定性と定量の両情報から分析し、予防保全の一部を事後保全(不具合または不具合可能性が高まった段階で更新または改修する保全方法のこと)に転換し、支出を抑える検討が求められます。
ただし注意しなければならないのは、事後保全に転換したことで支出がゼロになる訳では無く、来るべき事態に備え、修繕積立金に余力を有しておく必要があることは言うまでもありません。
3) 予防保全から予兆保全・予知保全への見直し
予防保全は支出が嵩む、事後保全はネガティブ要素が多すぎる、その様なケースで考える次なる手段が「予兆保全」や「予知保全」です。
予兆保全の代表例として、IoTの活用や点検によって設備の振動、温度、音などを監視し、異常の兆候が顕在化した時点で更新する方法があります。更新または改修するタイミングの見極めが難しいですが、支出を極限まで先延ばしできる可能性を生み出すことがメリットです。
また、最近ではAIの活用による予知保全も注目を浴びています。オフィスビルへの採用事例はまだそれほど多くありませんが、たとえば、空調設備の振動、運転電流、温湿度などのアナログデータの相互関係性をAIで解析し、人間が気づかない「通常とは異なる関係性」を検出した際に、対象部位の特定とともにアラートを上げるといった仕組みがあります。予兆保全よりも時間的にゆとりを持った対応が可能となるため、今後採用される事例が増えるのではないかと予想されます。

保全計画の実行~精度ある予算策定と柔軟な対応力~
策定された保全計画は実行段階(ここでは予算設定から発注までを指すこととします)でさらに精緻化されます。一般的には、長期修繕計画をベースに5年程度の中期計画を策定し、さらに単年度計画へと落とし込む過程を経て、更新工事や改修工事の仕様や工事費などの精度を高めていきます。実施前年度に予算額を設定し、当該年度にその予算額内で工事を行うルーティンが、どの施設においても定着、実行されているのではないでしょうか。
ここで我々が重視するのが予算額の設定方法です。
施設運営でありがちな悪い例として、要件定義を明確にしないまま、個人の経験や元施工業者からの提案に依存した工事仕様の策定や予算設定があります。これらは発注用見積り取得段階で工事費の大幅な上振れや下振れを招き、上振れであれば実施の見送り、下振れであれば他工事への投資機会損失といったリスクに繋がります。
そこで山下PMCは予算設定の段階で要件定義を明確化し、さらに社内専門チームのバックアップを受けて詳細な工事仕様、施工条件、スケジュールなどを策定し、これらを発注図書案に昇華させ、お客さまとレビューを行います。
レビューによってお客さまと合意形成が図られた次のステップとして、山下PMC独自のコストデータベースを活用したり、施工候補者に対しRFI(情報提供依頼書)を発行し参考工事費を取得するなどの手段により、精度の高い予算設定が実現します。
これによって投資の最適化が図られるだけでなく、実行年度において時間的ゆとりをもった発注作業が可能となるメリットが創出されます。

ストック型運用成功の鍵は、計画と実行の精度に宿る
今回、本コラムでは戦略的な保全マネジメントの一例をご紹介しました。
当社にはあらゆる分野に精通した施設の専門医=Facility Dr.が在席しており、紹介した事例以外の提案も数多く行っております。
今後もストック型社会における施設運営の最適解を追求し、持続可能な価値創造を実現してまいります。

山下PMC
環境・運営推進本部 1部CRE戦略部
チーフプロジェクトマネジャー
渡辺 和夫
次回の「The Report」は、山下PMC 池田 裕一郎がお届けします。
・記載されている内容は、掲載当時の情報です。予告なく変更する場合もございますので、あらかじめご了承ください。
・記載されている会社名、商品名は、各社の商標、または登録商標です。なお、本文中では™、®マークは基本的に明記していません。
 山下PMCの理念
山下PMCの理念